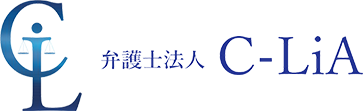実名と匿名とを問わず、今や世界中の人々が1つはSNSのアカウントを保有しており、動画共有サイト「YouTube」では、実在する人が顔を出して活動するいわゆるYoutuberのほか、架空のCGキャラクター(アバター)を生み出したうえでそのアバターにモーションキャプチャー技術により動きを与え、「中の人」として誰かが声をあてることにより活動するVtuber(バーチャルYoutuber)も登場し、活動・活躍の場を広げています。
そのため、実際に現実世界に存在する私たちのような「人」そのものだけではなく、匿名アカウントやVtuberのような電子の世界にのみ存在するアバターや架空人が、独自の意思を持って活動している場面が増えてきています。
それに伴い、TwitterやInstagram上での匿名アカウント同士でのインターネット上のトラブルであったり、YouTube上でのVtuberに対する誹謗中傷が増加しており、匿名アカウントを使っている人やVtuberとして活動している人が安心してインターネット上での暮らしを送るためには、匿名アカウントやVtuberのアバターに対して行われた誹謗中傷に対しても、適切に法的措置をとらなければならない場面が数多く存在します。
目次
Vtuberに対する誹謗中傷の事例・裁判
2022年8月31日、大阪地方裁判所において、Vtuberに対する誹謗中傷について、その誹謗中傷をした人の発信者情報を開示するように命じる判決が出されました。
朝日新聞デジタル
この裁判では、Twitterのフォロワー100万人を超えるVtuberとして活動する女性が、某匿名掲示板において「仕方ねぇよバカ女なんだから」「母親がいないせいで精神が未熟なんだろ」などと書き込みをされたことから、自分の名誉感情を侵害されたとして、書き込みをした者が利用したプロバイダに対し、書き込みをした者の情報を開示するよう発信者情報請求をしていました。
この他にも、Vtuberや匿名で仮面を被って活動するYoutuberによって、名誉毀損、名誉感情侵害(侮辱)を理由とする発信者情報開示請求の裁判は多数行われており、開示を認める裁判例が多数登場していることから、今後も同じようにYoutuber、Vtuberによる発信者情報開示請求は増加するものと思われます。
Vtuber・匿名アカウントに対する誹謗中傷の法的なポイント
インターネット上では、自分の顔も名前も知られてないし、相手と対面しているような状況でもないということから、普段の生活では絶対に他人に対して言うことのないような心無い言葉を投げかけてしまう人が少なくありません。この状況が、自分の気持ちを大きくさせ、まるで何を言っても許される偉い立場になったかのような錯覚を人に与え、また、相手がVtuberや匿名アカウントである場合には、相手が実在するものではないかのような認識をもってしまい、普通の人に対しては言わないような罵詈雑言をぶつけてしまうということもあります。
実際に、当事務所弁護士が担当した類似の事件でも、発信者情報開示請求を行った後、誹謗中傷となる投稿・コメントをしてしまった人からは「自分のコメントで傷つく人が存在する、ということを深く考えずにやってしまった。」というような言葉を出されたこともあります。
さて、改めてVtuberや匿名アカウントに対する誹謗中傷対策及び誹謗中傷に対する発信者情報開示請求で重要となるのは、対象となるコメントが誰に向けてされたものであるか、という点です。この点は、同定可能性と誹謗中傷の内容により構成される問題点です。
誹謗中傷に関する裁判においては、同定可能性というキーワードが多々登場します。この同定可能性というのが、対象となるコメント・投稿が、誰に対してなされたものであるかを客観的に判断することができるかどうかというもので、主に名誉毀損の場面で問題となります。
名誉毀損の場面
名誉毀損が成立するためには、対象となるコメント・投稿が、対象者の社会的評価を低下させることが必要となります。そして、そのコメント・投稿が匿名アカウントやVtuberに対してなされたものである場合、コメント自体が対象者の社会的評価を低下させるようなものであったとしても、実際に社会的評価が低下することになるのはいわゆる「中の人」ではなく、表に出ている匿名アカウントという架空人やVtuberのアバター・キャラクターではないのか、という問題があります。
この問題について、裁判所は、その匿名アカウントやVtuber自体が「中の人」と客観的に結びつく状況が必要であると考えており、基本的に「中の人」の情報を出さずに活動するVtuberとしては、この裁判所の理屈を乗り越えて名誉毀損の成立を主張することが難しい状況にあります。
名誉感情侵害(侮辱)の場面
では、上記で紹介した裁判例が間違っているのか、あるいは特殊な状況だったのかというと、そういうわけではありません。
名誉毀損と似ているものの、また別の法律違反として捉えられる行為に、名誉毀損侵害すなわち侮辱という行為があります。
この名誉感情侵害(侮辱)の場合には、先ほど述べました客観的な同定可能性というのは問題とならず、誹謗中傷コメントの対象者とされたVtuberや匿名アカウントが「あ、このコメント私に対して言っている。」ということが分かればいいとされています。無論、なんでもかんでも自分に対してなされたコメントであると主張すればいいわけではなく、客観的に見て、そのVtuberが「これは自分に対してなされた誹謗中傷コメントだ!」と理解できる状況である必要はあります。
このようにして、Vtuberや匿名アカウントが自分に対する誹謗中傷がなされていることを理解できれば、その誹謗中傷のコメント・投稿により心を傷つけられてしまい、精神的苦痛を受けることとなるのは、Vtuberや匿名アカウントの「中の人」になります。そのため、「中の人」は、誹謗中傷を理由として、コメント・投稿をした人に対して、損害賠償として慰謝料を求めることができる状態になります。
この理屈により、上記で紹介した裁判例も、Vtuberの慰謝料を請求する必要性を認め、その前提としてコメント・投稿をした人の情報が必要であることから発信者情報開示を認めたものと考えられます。今後同様の事件が起きたとしても、コメント・投稿の内容次第ではありますが、広く発信者情報開示請求の対象とすることができます。
誹謗中傷の内容
これらの理屈のほかに、上記で紹介した裁判例が問題としており、かつ主としてニュースで取り上げられている部分は、誹謗中傷の内容が「中の人」に対してなされたものなのかそれともあくまでVtuberのアバター・キャラクター設定部分に対してなされたものなのかという観点です。
今回の裁判例では、対象となったVtuberのアバター・キャラクターには「中の人」の個性や体験、経験が反映されていることから、そもそもこのアバター・キャラクターは「中の人」によってコントロールされた表現行為を行っているのだから、このアバター・キャラクターに対する誹謗中傷は、実質的には「中の人」に対して行われたものであると解釈し、名誉感情侵害(侮辱)の成立を認めました。
これが例えば「中の人」は男性なのにアバター・キャラクターが女性である場合に、「クソブス女」などのコメントがなされた場合には、また結論が異なる可能性があります。あくまで、誰が傷つけられたのか、というのを客観的に分析する必要があり、過去の裁判例を適切に分析したうえで個別具体的な事案に当てはめることができる能力が必要になります。
Vtuber事務所の対応
昨年12月に、「にじさんじ」と「ホロライブ」の有名Vtuberプロジェクトを手掛ける大手Vtuber事務所である「ANYCOLOR株式会社」と「カバー株式会社」がタッグを組み、これらの事務所に所属するVtuberに対する誹謗中傷への対応体制を構築することを発表しています。
(参照:にじさんじ、ホロライブ運営が「誹謗中傷の根絶」で連携。VTuberの“心と人生”守るために(参照元:BUSINESS INSIDER)
フットワークが軽く、柔軟な対応をとることができるベンチャー企業らしく、今回の提携は事務所に所属するVtuberにとっても非常に安心できるものといえるでしょう。
これらの事務所に所属していないVtuberであっても、大手が率先して誹謗中傷対策をとることにより、ある意味ではそれが風よけとなって誹謗中傷の被害に遭う可能性も低くなることが予想されます。
もっとも、いざ誹謗中傷が起きてしまった場合、特に上記事務所に所属していない場合には、自ら対応を取らなければならないという場面も出てくることが考えられます。
Vtuber・匿名アカウントが誹謗中傷を受けたら…
Vtuberとして活動されている方や匿名アカウントを利用している方が、Twitter、Instagram、YouTube、匿名掲示板(5ちゃんねる等)において誹謗中傷を受けた場合には、速やかに発信者情報開示請求を行わなければなりません。
といいますのも、誹謗中傷のコメントや投稿については、多くの場合そのコメントや投稿がされてから3か月も経てば、投稿をした人の情報が消えてしまうためです。
一般的には仮処分手続という裁判手続を利用することにより投稿者のIPアドレスを割り出し、その後に訴訟手続を利用してそのIPアドレスを割り当てられているインターネットサービスプロバイダから契約者情報の提供を受けることになります。このIPアドレスを取得し、プロバイダに連絡することによって投稿した人の契約者情報の保護を依頼すればひとまず時間制限のハードルはクリアできるのですが、仮処分手続に必要な時間を考えると、コメントや投稿がされてから1か月程度のうちには仮処分手続の申立てをしておきたいです。
2022年10月より、新しい発信者情報開示の制度が利用できるようになることから、従来よりは簡易かつ迅速な手続により発信者の情報を得ることができると言われていますが、上記の3か月という時間制限については変わりなく、あくまでスピードアップするのは、最初の手続を申し立ててから発信者の情報を獲得するまでの期間にすぎません。
また、サイトあるいはSNSの種類によっては、その新しい発信者情報開示の制度は適当ではなく、従来型の仮処分手続をスタートとしなければならないこともあり、より一層どのような対応をとるべきかという点についてのノウハウが重要となってきます。
そのため、専門的かつ複雑な発信者情報開示の手続においては、この分野を専門として知識・経験を有する弁護士に依頼することが必要不可欠であり、一度消えてしまった契約者情報は元に戻すことがシステム上・技術上・法律上不可能であることから、誹謗中傷をされたと感じた場合には、すぐに弁護士にご相談ください。
なお、個別のSNS、匿名掲示板についての対策・開示手続については、下記の記事で解説しておりますので是非ご一読ください。
X(旧Twitter)に対する発信者情報開示手続|誹謗中傷・著作権侵害・肖像権侵害
Instagram(インスタグラム)に対する発信者情報開示手続|誹謗中傷・著作権侵害・肖像権侵害
匿名掲示板における誹謗中傷と対策|発信者情報開示請求を中心に
当事務所でも、Youtuber、Vtuber、インフルエンサー等のインターネット上で活動されるクライアント様の発信者情報開示、削除等の案件を多数取り扱っており、きっとお力になることができると思います。Youtube、Vtuber、インフルエンサーあるいはこれらに該当しない方であっても、誹謗中傷に関する初回相談は無料となりますので、ご遠慮なくお問い合わせください。